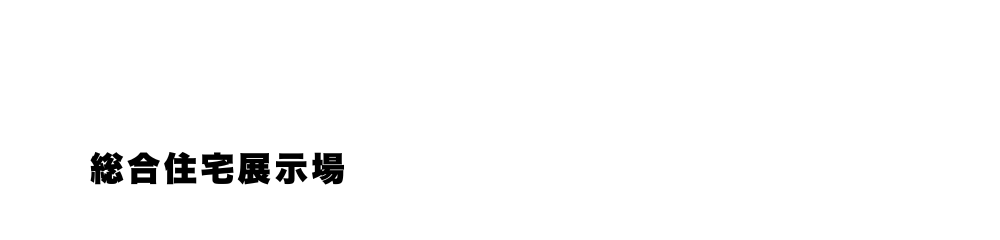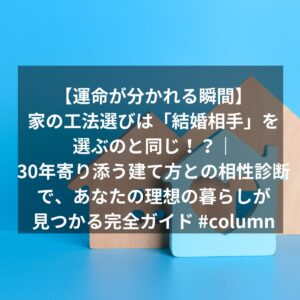新築2年目の真実:コンセント配置で「成功した3箇所」と「大失敗した5箇所」を全部見せます #column
この記事を読めば分かること
この記事では、新築住宅のコンセント設計について、以下のことが実践的に分かります。
- 実際に住んでみて初めて分かる「コンセントの真の価値」
- 成功と失敗を分けた決定的な判断基準の違い
- 家族構成別に見る「これだけは外せない」絶対条件
- プロが教えてくれない「住んでからの変化」への対応法
- 美しさと利便性を両立させる「見えない電源」の作り方
- 限られた予算で最大の効果を出す戦略的優先順位
はじめに
「ねえ、これ見て」
引っ越して3ヶ月目の夜、夫が私にスマホの画面を見せました。
家計簿アプリです。「延長コード・電源タップ」というカテゴリーに、28,000円と表示されていました。
「3ヶ月で、これだけ買ってるんだよ」
6口タップ、3口タップ、長めの延長コード、USB付きタップ、個別スイッチ付きタップ…。新居に引っ越してから、次々と買い足していました。
「コンセント足りないからって、こんなに…」
そうなんです。私たちは、新築時にコンセントをケチったせいで、結果的にもっとお金を使っていたんです。
それだけではありません。
リビングの床には、3本の延長コードが這っています。先週、2歳の息子がそれに引っかかって転びました。幸い軽傷でしたが、ヒヤッとしました。
夫婦でノートパソコンを使いながら仕事をしたいとき、コンセントの奪い合い。「先に使ってた」「こっちが急ぎなのに」。コンセント一つで、夫婦喧嘩です。
Pinterest で憧れていたミニマルなインテリア。でも現実は、コード類が視界に入り、生活感満載の部屋に。
「こんなはずじゃなかった」
7,200万円かけて建てたマイホーム。でも、たった数万円をケチったコンセントのせいで、毎日小さな不満が積み重なっていく。
ただ、全てが失敗だったわけではありません。
キッチンのコンセント配置は、ほぼ完璧でした。設計士さんの提案を素直に聞いた結果です。
寝室のベッド周りも、まあまあ成功。ここは自分たちでしっかり考えた部分でした。
つまり、成功したところと失敗したところには、明確な「違い」があったんです。
この記事では、その「違い」を徹底的に分析します。
なぜキッチンは成功して、リビングは失敗したのか? なぜ寝室は及第点で、洗面所は大失敗だったのか?
成功例と失敗例を両方見せることで、あなたが「何を大切にすべきか」が見えてくるはずです。
私の失敗を、あなたの成功に変えてください。
成功事例①:キッチンの「3層コンセント戦略」が生んだ奇跡
我が家で唯一、100点満点と言えるのがキッチンのコンセント配置です。
設計時の決断
設計士さんに言われました。
「キッチンは、一般的な家の2倍のコンセントを付けることをおすすめします」
当時の私たちは悩みました。
「2倍?そんなに要る?予算もあるし…」
でも、設計士さんは説得力のある説明をしてくれたんです。
「今お使いの家電は何個ですか?」
「えっと…冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、トースター、ケトル。5個ですね」
「では、3年後は?お子さんが成長して、料理の幅も広がります。ホームベーカリー、フードプロセッサー、コーヒーメーカー…増えていきませんか?」
「…確かに」
「キッチンは、家電が最も増える場所なんです。最初から余裕を持たせておかないと、後から困ります」
結局、私たちは設計士さんの提案を全面的に受け入れました。
実際の配置
キッチンのコンセント:合計18口
下層(床から25cm):8口
- 冷蔵庫専用×1
- 炊飯器、ケトル、トースター用×4
- 食洗機×1
- 予備×2
中層(カウンター上、床から95cm):6口
- ハンドブレンダー、フードプロセッサー用×3
- タブレット(レシピ見る用)×1
- 予備×2
パントリー内:4口
- ホームベーカリー×1
- ミキサー×1
- 予備×2
2年後の現在
下層:8口中7口使用中
- 冷蔵庫、炊飯器、ケトル、トースター、電子レンジ、食洗機、コーヒーメーカー
中層:6口中4口使用中
- ハンドブレンダー、フードプロセッサー、タブレット、電気圧力鍋
パントリー:4口中3口使用中
- ホームベーカリー、ミキサー、ヨーグルトメーカー
合計:18口中14口使用、余裕4口
完璧です。延長コード不要。すべての家電に定位置があり、使いたいときにすぐ使えます。
成功の要因分析
なぜキッチンは成功したのか?3つの要因があります。
要因1:専門家の意見を素直に聞いた
設計士さんは、何十軒もの家を手がけています。「キッチンは家電が増える」という経験則を持っていました。
それを疑わず、素直に受け入れた。これが最大の勝因です。
要因2:「高さ」を3段階に分けた
床レベル、カウンターレベル、収納内。
この3層構造が、使い勝手を劇的に向上させました。
常設家電は床レベル。調理中に使う家電はカウンターレベル。たまに使う家電は収納内。
この使い分けができているから、キッチンがスッキリしているんです。
要因3:パントリー内のコンセントが「隠す収納」を実現
これが最高のアイデアでした。
ホームベーカリーは、使うのは週末だけ。でも置き場所を取ります。
パントリー内にコンセントがあるおかげで、使わないときは扉の中へ。使うときだけ取り出して、その場で電源オン。
「隠せる」けど「すぐ使える」。この両立が、キッチンの美しさを保っています。
具体的な使用シーン
日曜の朝、パン作り。
パントリーの扉を開ける→ホームベーカリーを取り出す(すでに充電されている)→カウンターに置く→材料を入れてスタート。
わずか30秒。延長コードを探す必要も、別の家電のコンセントを抜く必要もありません。
これが「余裕のあるコンセント設計」の威力です。
成功事例②:寝室の「両サイド独立型」が夫婦円満を守った
寝室も、比較的成功した事例です。
設計時の決断
寝室のコンセントは、自分たちで考えました。
「ベッドの両側に、それぞれ4口ずつ付けよう」
合計8口。当時は「多いかな?」と思いました。でも、結果的にこれが正解でした。
実際の配置
ベッド右側(夫側):4口
- スマホ充電×1
- スマートウォッチ充電×1
- ノートPC充電×1
- ベッドサイドランプ×1
ベッド左側(妻側):4口
- スマホ充電×1
- タブレット充電×1
- 電子書籍リーダー充電×1
- ベッドサイドランプ×1
2年後の現在
右側:4口すべて使用中(冬は電気毛布も使いたいが、1口足りない) 左側:4口すべて使用中(加湿器も使いたいが、1口足りない)
評価:80点
ギリギリですが、日常使用では問題ありません。ただし、冬季の暖房機器を使う余裕がないのが惜しい。
成功の要因分析
要因1:「夫婦それぞれ」という発想
これが最大の成功要因です。
寝室のコンセントを「2人で共有」ではなく、「それぞれ独立」で設計したこと。
夫は右側で自分のデバイスを充電。妻は左側で自分のデバイスを充電。お互いに干渉しません。
「コンセント使ってる」「ちょっと貸して」という会話がゼロ。これが夫婦円満の秘訣です。
要因2:高さを「手が届く位置」に設定
床から60cm。
これが絶妙でした。
ベッドに横になったまま、軽く手を伸ばせば届く。起き上がる必要がありません。
夜中にスマホを充電し忘れたことに気づいても、ベッドから出ずに対応できます。
標準的な床から25cmの位置だったら、毎回起き上がる必要があったでしょう。
要因3:ベッドサイドテーブルとの連動設計
コンセントの位置を決めるとき、ベッドサイドテーブルの高さを考慮しました。
テーブルの天板は床から55cm。コンセントは床から60cm。
つまり、コンセントはテーブルのすぐ上。充電ケーブルが短くて済み、見た目もスッキリです。
改善点
80点なので、20点分の改善余地があります。
改善点1:もう1口ずつ追加すべきだった
各サイド5口にしておけば、冬の暖房機器にも対応できました。
予算的には、たった6,000円の差(2口×3,000円)。
この6,000円をケチったせいで、冬は延長コードを使っています。
改善点2:USB充電ポート付きコンセントにすべきだった
最近のコンセントには、USB充電ポートが組み込まれたものがあります。
これにしておけば、充電アダプターが不要で、見た目がもっとスッキリしたはずです。
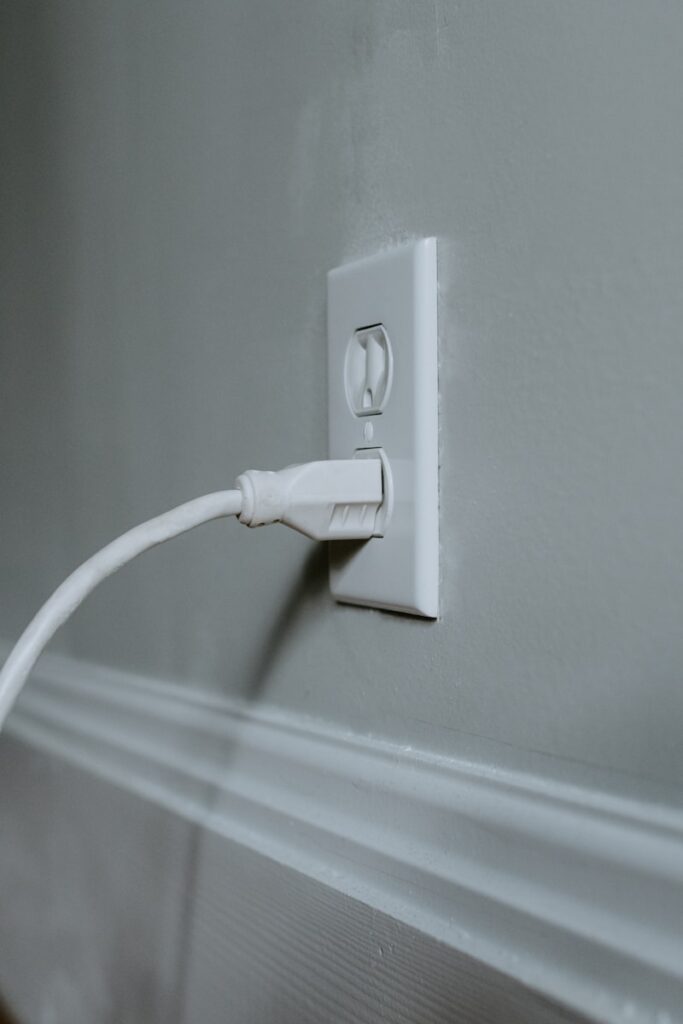
成功事例③:子ども部屋の「壁面4分割戦略」が模様替えを自由にした
子ども部屋(娘・小2)も、意外と成功しています。
設計時の決断
「子ども部屋は、将来どうなるか分からない。だから、どこに家具を置いても対応できるように」
この方針で、コンセントを4つの壁に分散させました。
実際の配置
北壁(窓側):3口 東壁(ドア側):2口 南壁(クローゼット側):2口 西壁(机予定地):4口
合計:11口
2年後の現在
当初の予定:西壁に学習机を配置 実際:北壁(窓側)に学習机を配置
娘が「窓の外を見ながら勉強したい」と言い出し、配置を変更。
でも、北壁にも3口あったので、問題なく対応できました。
成功の要因分析
要因1:「分からないから、分散させる」という戦略
子どもの好みは変わります。成長と共に、必要な家具も変わります。
だから、「どこに何を置くか」を確定させず、柔軟性を持たせたこと。これが大正解でした。
要因2:「年齢×0.5+4」の法則
これは設計士さんから教わった法則。
子どもの年齢に0.5をかけて、4を足す。これが子ども部屋の推奨コンセント数。
娘は当時6歳。6×0.5+4=7口
でも、将来を見越して11口にしました。
現在8歳。8×0.5+4=8口
実際に使っているのは9口。まだ2口余裕があります。
中学生(13歳)になると:13×0.5+4=10.5口
ちょうど11口でカバーできる計算。完璧です。
要因3:クローゼット内にも確保
南壁の2口は、クローゼットの中。
ここに除湿機とコードレス掃除機の充電スタンドを設置。
部屋から見えないので、子ども部屋が散らかって見えません。
失敗事例①:リビングの「ソファ難民問題」で家族がバラバラに
一方、失敗例もあります。最大の失敗がリビング。
設計時の判断
「リビングは広いし、コンセントも適当にあれば大丈夫でしょ」
深く考えず、標準的な配置にしました。
実際の配置
- テレビ周り:6口
- ダイニング側の壁:3口
- 窓側の壁:2口
合計:11口
一見、十分に見えます。でも…
2年後の現在
夜8時のリビング
私:ソファに座りたい。でもスマホの充電が15%。コンセントはソファから4メートル離れた壁。
結果:床に座って充電しながらスマホを使う。腰が痛い。
夫:ノートPCで仕事したい。でもダイニングテーブルの近くにしかコンセントがない。
結果:ダイニングテーブルで作業。家族と離れた場所に。
娘:タブレットで動画を見たい。でも充電が必要。
結果:テレビの近くの床に座り込む。ソファに座れない。
息子:おもちゃで遊びたいけど、みんなが散らばっていて落ち着かない。
結果:一人で子ども部屋へ。
家族4人が、同じリビングにいるのに、バラバラの場所にいる。
これが「ソファ周りにコンセントがない」ことの結果です。
失敗の要因分析
要因1:「ソファでくつろぐ」という行動を想像しなかった
図面を見ながら、「ここにコンセント、あそこにコンセント」と機械的に決めました。
でも、「ソファに座って、スマホを充電しながらくつろぐ」という具体的なシーンを想像しなかった。
これが最大の失敗です。
要因2:「テレビ周りにあれば十分」という思い込み
「リビングの電源はテレビ周りに集中させればいい」
この思い込みが、失敗を招きました。
現代のリビングは、テレビを見るだけの場所ではありません。
スマホを使う、タブレットを使う、ノートPCを使う。それぞれが違うデバイスで、違うコンテンツを楽しんでいます。
だから、電源も分散して必要なんです。
要因3:家具の配置を「なんとなく」決めた
ソファの位置を、正確にシミュレーションしませんでした。
「だいたいこの辺」という感覚で決めた結果、ソファから最も近いコンセントまで4メートルも離れてしまいました。
改善策(実施済み)
2年間我慢しましたが、ついに追加工事を依頼しました。
ソファ側面の壁に4口追加
費用:52,000円
- 出張費:8,000円
- 配線工事:18,000円
- 壁開口・復旧:15,000円
- 内装補修:11,000円
新築時に付けていれば:3,000円×4=12,000円
差額:40,000円の損失
高い授業料でした。
失敗事例②:洗面所の「朝の戦争」で家族関係が険悪に
洗面所は、最悪の失敗でした。
設計時の判断
「洗面所?ドライヤーと洗濯機用があれば十分でしょ」
コンセント:3口のみ
2年後の現在
平日の朝7時15分
私:髪を乾かしたい(ドライヤー) 夫:髭を剃りたい(電気シェーバー) 娘:音楽を聴きたい(スマホ、Bluetoothスピーカー)
必要:3口 実際:3口
一見、足りているように見えます。でも…
私の電動歯ブラシ:充電中 夫の電動歯ブラシ:充電中 娘の電動歯ブラシ:充電中
充電だけで3口使用。つまり、使える口はゼロ。
結果:充電器を抜いて、使って、また充電器を挿す。毎朝3回繰り返し。
しかも、家族4人が同じ時間帯に集中するため、順番待ち。
「早くして!」 「まだ?」 「私が先に使ってたのに!」
毎朝、洗面所から家族の怒号が響きます。
失敗の要因分析
要因1:「充電器の存在」を忘れていた
ドライヤーや電気シェーバーなど、「使うときに挿す」機器だけを考えていました。
でも、電動歯ブラシのように「常に充電しておく」機器の存在を忘れていたんです。
要因2:「家族全員が同時に使う」ことを想定していなかった
朝7時〜8時は、全員が洗面所に集中します。
この「ピークタイム」の電力需要を計算していませんでした。
要因3:将来の変化を考えなかった
設計時、息子はまだ0歳。電動歯ブラシは使っていませんでした。
でも今、息子も2歳。子ども用電動歯ブラシを使い始めました。
電動歯ブラシは4台に。でもコンセントは3口のまま。完全にキャパオーバーです。
改善策(検討中)
洗面所の追加工事も検討していますが、難しい点があります。
洗面所は狭い。壁の裏に配管が集中している。追加工事のコストが高い(見積もり:78,000円)。
現在は、寝室から延長コードを引いて対応。見た目も悪いし、危険も感じます。
新築時に6口付けていれば:18,000円
差額:60,000円の損失(予定)
失敗事例③:書斎の「在宅ワーク想定外」で仕事効率が半減
書斎(というか、リビングの一角のワークスペース)も失敗でした。
設計時の判断
「在宅ワークは週1日だけだし、ノートPCとデスクライトがあれば十分」
コンセント:4口
2年後の現在
パンデミックの影響で、在宅ワークが週4日に。
必要な機器:
- ノートPC本体
- 外付けモニター×2
- デスクライト
- スマホ充電(仕事用)
- スマホ充電(私用)
- ウェブカメラ
- 外付けマイク
- 外付けハードディスク
- プリンター
必要:9口 実際:4口 不足:5口
結果:延長コード2本で対応。デスクの下はコードの海。
見た目も悪いし、掃除もしにくい。何よりプロフェッショナルに見えない。
オンライン会議中、カメラに延長コードが映り込んで恥ずかしい思いをしました。
失敗の要因分析
要因1:「2020年の常識」で判断してしまった
家を建てたのは2021年。当時、在宅ワークは「たまにやるもの」でした。
でも2022年以降、働き方が大きく変化。週4日在宅が当たり前に。
この「未来の変化」を予測できませんでした。
要因2:「周辺機器」を軽視した
「ノートPCとデスクライトだけ」と考えていました。
でも実際は、モニター、カメラ、マイクなど、周辺機器がどんどん増えました。
オンライン会議の品質を上げるために、外付け機器は必須。これを想定していませんでした。
要因3:「美しさ」を考えなかった
4口のコンセントは、すべて床から25cmの位置。
結果、9個の機器のコードが壁から床に垂れ下がり、デスクの下で絡まり合っています。
デスクの高さ(床から70cm)にコンセントを設置していれば、コードが短く済んで、見た目もスッキリしたはずです。
改善策(実施済み)
壁面配線ダクトの設置
コンセント追加工事は高額すぎるため、別の方法を選びました。
デスクの背面に、配線ダクト(8口)を設置。コスト:18,000円
見た目は改善しましたが、根本的な解決ではありません。配線ダクト自体が見えるため、完全にスッキリとは言えません。
最初から、デスクの高さに8口のコンセントを埋め込んでいれば:24,000円
ほぼ同じコストで、もっと美しい解決ができたはずです。
失敗事例④:ダイニングの「ホットプレート問題」で週末が憂鬱に
最後の失敗例は、ダイニング。
設計時の判断
「ダイニングテーブルの近くにコンセント?要らないでしょ」
コンセント:0口(最寄りは3メートル先の壁)
2年後の現在
週末、ホットプレートで食事を楽しみたい。
でも、コンセントが遠い。
選択肢は2つ
- 延長コードを3メートル引っ張る→床を這うコードに家族が引っかかりそう
- ダイニングテーブルをコンセント近くに移動→テーブルが窓から離れて暗くなる
どちらも不満足。
結果:ホットプレートを使う頻度が激減。月2回→月0.5回に。
失敗の要因分析
要因1:「ダイニング=食事だけ」という固定観念
ダイニングテーブルは、食事をする場所。そう思い込んでいました。
でも実際は、ホットプレート料理、子どもの工作(電動ドリル使用)、在宅ワーク(ノートPC)など、多目的に使います。
この多様性を想定していませんでした。
要因2:「友人の家」を見学しなかった
家を建てる前、もっと友人の家を見学すべきでした。
後から知ったのですが、最近の家の多くは、ダイニングに床埋め込み式コンセントを設置しています。
この存在を知らなかったんです。
要因3:設計士さんに質問しなかった
設計士さんは提案してくれませんでした。でも、こちらから「ダイニングにコンセント必要ですか?」と聞けば、アドバイスをくれたはずです。
質問しなかった自分の責任です。
改善策(諦めた)
床埋め込み式コンセントの追加
見積もり:125,000円
- 床の開口
- 配線工事
- 床材の補修
高すぎて諦めました。
新築時なら:20,000円
差額:105,000円
これが最も「やっておけば良かった」と後悔している部分です。
失敗事例⑤:収納内コンセントの「付け忘れ」で美観が崩壊
最後は、収納内のコンセント。
設計時の判断
「収納の中にコンセント?何に使うの?」
全ての収納に、コンセント:0口
2年後の現在
パントリー、シューズクローク、リビング収納、すべて「コンセントがあれば便利なのに」と思っています。
パントリー:ホームベーカリーを収納したいが、コンセントがないため、カウンターに出しっぱなし→生活感が出る
シューズクローク:電動自転車のバッテリーを充電したいが、コンセントがないため、リビングまで運ぶ→重くて大変
リビング収納:ルンバの充電基地にしたいが、コンセントがない→リビングの隅に充電基地→見た目が悪い
失敗の要因分析
要因1:「収納=物を置くだけ」という認識
収納は、物を置くだけの場所。そう思っていました。
でも実際は、「使わないときは隠しておきたい家電」の置き場所でもあったんです。
要因2:Pinterest の「収納内コンセント」画像を見ていなかった
後から知りましたが、収納内コンセントは、おしゃれな家の定番テクニック。
家を建てる前に、もっと情報収集すべきでした。
要因3:「隠す」という発想がなかった
生活感のある家電を「隠す」という発想がありませんでした。
「使うんだから、出しておけばいい」
そう思っていましたが、実際に住んでみると、「見せたくない家電」がたくさんあることに気づきました。
改善策(一部実施)
パントリーにコンセント追加
費用:45,000円
これで、ホームベーカリーとミキサーを隠して収納できるようになりました。
新築時なら:12,000円(4口)
差額:33,000円
シューズクロークとリビング収納は、予算の都合で諦めました。
「成功と失敗」を分けた3つの決定的な違い
成功事例と失敗事例を見てきました。
両者には、明確な「違い」があります。
違い①:専門家の意見を聞いたか?
成功したキッチン:設計士さんの提案を全面的に受け入れた
失敗したリビング・洗面所・書斎・ダイニング:自分たちだけで判断した、または設計士に質問しなかった
教訓:専門家は理由があって提案しています。まず聞く。理由を理解する。それから判断する。
違い②:具体的な生活シーンを想像したか?
成功した寝室:「ベッドに横になったまま、スマホを充電したい」という具体的なシーンを想像した
失敗したリビング:「ソファでくつろぎながら充電したい」というシーンを想像しなかった
教訓:図面だけで判断しない。「その場所で何をするか」を、映画のシーンのように具体的に想像する。
違い③:将来の変化を考慮したか?
成功した子ども部屋:「子どもの好みは変わる」「成長と共に機器が増える」ことを想定した
失敗した書斎:「在宅ワークが増える」「周辺機器が増える」ことを予測できなかった
教訓:今だけで判断しない。5年後、10年後を想像する。予測できないなら、余裕を持たせる。
「もし今、ゼロから設計できるなら」の完全プラン
2年間の経験を踏まえて、「もし今、ゼロから設計できるなら」という完全プランを作りました。
玄関・シューズクローク:4口
- 掃除機用×1
- 電動自転車バッテリー×2
- 予備×1
リビング:20口
- テレビ周り×6
- ソファ右側×5
- ソファ左側×5
- その他×4
ダイニング:3口
- 床埋め込み式×2
- 壁面×1
キッチン:18口(現状維持、完璧)
- 下層×8
- 中層×6
- パントリー内×4
洗面所:8口
- 洗面台周り(高さ100cm)×4
- 洗面台下(充電器用)×3
- 洗濯機周り×1
主寝室:10口
- ベッド右側(高さ60cm)×5
- ベッド左側(高さ60cm)×5
子ども部屋×2:各11口(現状維持、成功例)
書斎/ワークスペース:12口
- デスク高さ(70cm)×8
- デスク下×4
廊下・階段:3口
- 1階廊下×1
- 階段中間×1
- 2階廊下×1
収納内コンセント:10口
- パントリー×4
- シューズクローク×2
- リビング収納×2
- 寝室クローゼット×2
トイレ×2:各1口
ベランダ:2口
合計:112口
現在:58口 理想:112口 差分:54口
追加コスト(新築時):162,000円
2年間で、延長コード・電源タップに使った金額:28,000円 改善工事に使った金額(予定含む):195,000円
合計:223,000円
最初から完璧に設計していれば、61,000円の節約になりました。
それだけでなく、2年間のストレスもゼロにできました。
まとめ:コンセント配置は「未来の自分への手紙」
新築から2年。私は毎日、床を這う延長コードを見ながら、こう思います。
「2年前の自分に、伝えたい」
もっと設計士さんに質問して もっと具体的に生活シーンを想像して もっと将来の変化を考えて
でも、タイムマシンはありません。
だから、この記事を書きました。
あなたが、私と同じ後悔をしないように。
この記事で伝えた10の教訓
- 専門家の意見は理由を聞いてから判断する
- 図面だけでなく、具体的な生活シーンを映像で想像する
- 「今」ではなく「5年後、10年後」で設計する
- キッチンは家電が増える前提で2倍のコンセントを
- 洗面所は「家族全員×1.5+3」の法則で計算する
- リビングはソファ周りを最優先で考える
- 寝室は「夫婦それぞれ独立」で設計する
- 子ども部屋は「分からないから分散」させる
- 収納内コンセントは「隠す収納」の必須アイテム
- 建築後の追加工事は10〜15倍のコストがかかる
最後のメッセージ
家づくりは、人生で一度か二度の大きな決断。
その中で、コンセントは最も地味な存在です。
でも、毎日の幸福度を決めるのは、こうした「地味な部分」の積み重ね。
私は失敗しました。
でも、あなたは成功できます。
この記事が、あなたの「成功」の助けになれば、私の失敗にも意味があります。
2年後のあなたが、過去のあなたに「ありがとう」と言える。
そんな家づくりを、心から願っています。